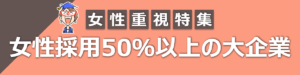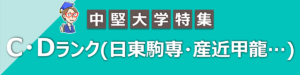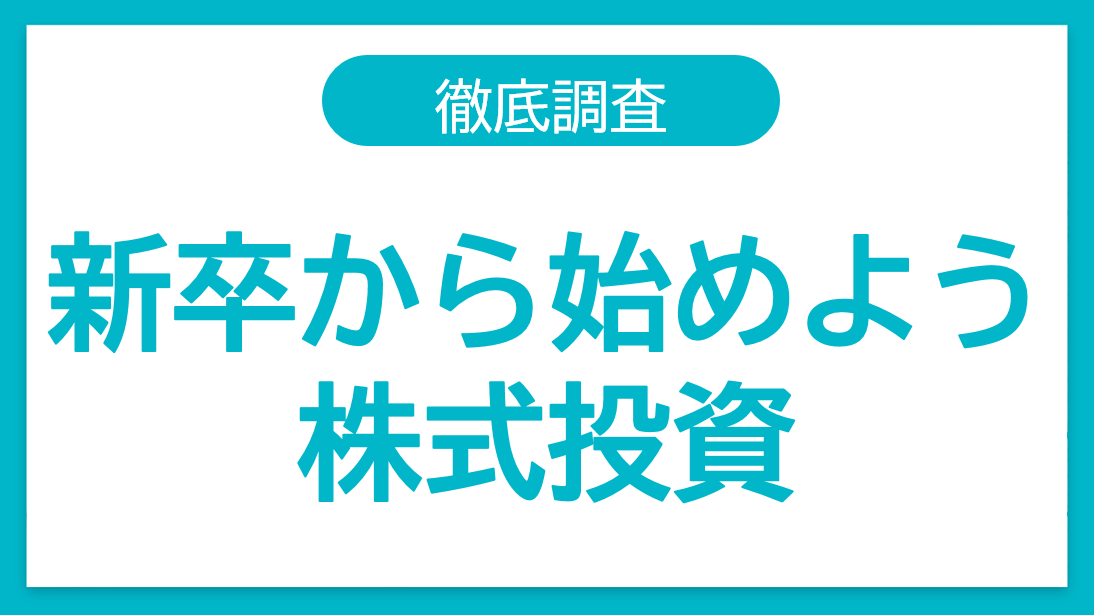公的年金は財政的に厳しいところがあり、今後は支給額が引き下げられていく可能性があります。
ゆとりのある老後を送るためには、自ら資産運用により資金を増やしておくことも大切です。
そこで今回は、その方法の一つとして考えられる株式投資について、押さえておきたいポイントをまとめて解説していきます。
株式投資に興味がある人は、本記事で解説する基本をチェックしてみていただければと思います。
株式投資であげられる3つの利益
株式投資を通じてあげられる利益には、以下の3つがあります。
- 売却益
- 配当金
- 株主優待
それぞれの意味を理解するために、株式会社の仕組みについて確認していきましょう。
そもそも株式の購入とは、株式会社の一部を所有することを意味します。
例えば、発行済み株式数が1万株のA社の株式を100株購入すると、A社の1%(=100株÷1万株)を所有することになります。
これを単純化して言えば、A社が事業で100万円の利益をあげれば、その1%の1万円分についてはあなたが所有権を持つことになるということです。
お金で買ったA社の事業から利益が生み出されるということで、「お金にA社で働いてもらう」というイメージを持つと分かりやすいかもしれません。
なお、会社が積み上げた利益は、会社全体で使い道を決めることになっており、株主個人が自由に引き出すことはできません。
会社全体で「1株あたりいくら分配しよう」と決めて、“配当金”という形で株主は利益から現金を受け取ることになります。
ちなみに、この利益からの分配とは別に、“株主優待”という形で自社のサービスなどを無料あるいは割引で提供しているような会社もあります。
A社が上場していると、こういった権利を持つ株式が市場において取引され、買いたい人と売りたい人のバランスによって株価が変動していきます。
「事業が好調になりそうだ」と考える人が増えれば買いたい人が多くなり、株価も上がっていきます。
株式を安く買い高く売ることで、“売却益”を狙うこともできるわけです。
銘柄を選ぶ際の5つのポイント
株式の価値の根本にあるのは、「その事業がどれだけ利益をあげられそうか」ということです。
この点、興味のある分野であればその事業がうまくいくかどうかのイメージを持ちやすく、株式投資において有利になることがあるかもしれません。
「遠くのものは避けよ」という投資の格言もあります。
特に初めのうちは、自分が興味を持てる商品やサービスを提供している会社から投資する候補を探すのがいいでしょう。
その上で、実際に銘柄を選ぶ際にチェックしておきたい主要なポイントとしては、以下の5つが挙げられます。
- 会社の事業概要
- 会社の業績
- 株価水準
- 配当や株主優待
- 最新ニュース
それでは、上記のポイントについて一つずつ説明していきます。
会社の事業概要
最初にチェックしておきたいのが、「その会社が一体どんな事業をやっているのか」ということです。
いきなり細かいところまで理解しようとせずに、全体像を把握することを意識しましょう。
「会社がどんな事業で利益をあげているのか」
「今後は何に注力していこうとしているのか」
「何か懸念材料はないか」
など、大まかなイメージで問題ありません。
上場会社であればホームページがあるはずなので、そこから投資家向け情報をチェックすることもできます。
この最初のステップは、自分が興味のある会社であれば楽しみながらできるはずです。
会社の業績
会社の全体像を把握したら、もう少し細かく会社の業績を見ていくといいでしょう。
上場企業は毎年決算報告書を公表することになっているので、それを確認すれば会社の業績や資産状況をチェックすることができます。
初めは難しく感じるかもしれませんが、記載される内容は決まっているので、意外と慣れるのは早いかもしれません
まずは、「売上高が伸びているか」「利益は増えているか」といった分かりやすいところから押さえていって、徐々に深い分析にも挑戦していってください。
ここでは、参考にできそうな指標を2つ挙げておきます。
| 指標 | 内容 |
| EPS(Earnings Per Share) | 1株当たりの当期純利益のことで、会社が1年間であげた利益を発行済み株式数で割って求めます。読み方は「イーピーエス」。 |
| ROE(Return On Equity) | 自己資本利益率のことで、会社が1年間であげた利益を自己資本(≒株主の持ち分合計)の額で割って求めます。読み方は「アールオーイー」。 |
株価水準
いくら業績の良い会社でも、人気が出てしまい株価が実力以上に上がってしまうと、投資が失敗する可能性が高まります。
そのため、業績をチェックすると同時に、それに見合った株価かどうかについてチェックしておくことも忘れてはいけません。
なお、業種や市場(東証一部、東証二部、JASDAQなど)などによって、株価水準が異なることもあります。
そのため、同業他社や同一市場内で比較すると、より効果的な分析ができるでしょう
ここでは、株価水準をチェックする際の基本的となる指標を2つ紹介しておきます。
| 指標 | 内容 |
| PER(Price Earnings Ratio) | 株価収益率のことで、会社が1年間であげた利益に対して株価が何倍の水準にあるかを示した値です。読み方は「ピーイーアール」。 |
| PBR(Price Book-value Ratio) | 株価純資産倍率のことで、会社の純資産(=会社の資産-会社の負債)に対して株価が何倍の水準にあるかを示した値です。読み方は「ピービーアール」。 |
配当金や株主優待
配当金や株主優待は、株式を保有し続けることで得られる利益です。
株式を売却するまでどうなるか分からない売却益と違い、受け取った時点で利益が確定します。
特に長期投資をする人にとっては、確実に利益を積み上げられるという意味で重要と言えるでしょう。
そのため、会社が株主に対してどういった還元政策を取っているかは、しっかり押さえておきたいところです。
なお、配当金に関して参考にできる指標として、ここでは以下の2つを挙げておきます。
| 指標 | 内容 |
| 配当利回り | 1年間で受け取る配当金が株価の何割かを示した値です。なお、これに株主優待分も加味して分析するのもいいかもしれません。 |
| 配当性向 | 会社が1年間であげた利益のうち、配当金に回した割合を示した値です。なお、成長企業などは利益を投資に回す方が望ましいケースもあり、配当性向が低いから悪いというわけではありません。 |
最新ニュース
最後に、会社に関する最新の動向についてもしっかりチェックしておくことをおすすめします。
これは株式購入時だけでなく、保有中についてもです。
もし重要な情報を見逃していると、大きな損失につながることがあるかもしれません。
上場企業は、株価が大きく変動する原因となるようなことが起きた場合、その情報を投資家に知らせることになっています。
こういった情報はきちんとチェックして、会社の最新の状況を把握しておくことが大切です。
リスクを抑える3つの基本
株式投資にはリスクが伴い、必ず利益があげられるとは限らず、時には損失が発生してしまうこともあります。
具体的には、株価が下がるリスク、会社が倒産するリスクなどがあります。
一般的に、これらのリスクを抑える方法として、以下の3つが知られています。
- 長期投資
- 分散投資
- 積立投資
それぞれについて、簡潔に説明していきます。
長期投資
長期投資とは、購入した株式を長期間にわたって保有し続ける投資方法です。
株価は短期的に上下動することがありますが、それに左右されて短期的に売買を繰り返していると、損失がかさんでしまう可能性があります。
一方、長期的に保有していれば、短期的な上下動に左右されないことに加え、配当金などの利益も積み上がっていくため、損益が安定しやすくなると考えられます。
分散投資
分散投資とは、さまざまな銘柄を少しずつ購入する投資方法です。
そうすることで、仮に株価が下がった銘柄があっても、他の銘柄の株価は上がっている可能性があるため、全体としての損益が安定することが期待できます。
なお、株式の中で分散投資することもできますが、債券や投資信託など、別の金融商品に投資対象を広げるという形も考えられます。
積立投資
積立投資とは、少しずつ定期的に長期にわたって株式を購入し続ける投資方法です。
購入する時間を分散させることによって、株価を高いところだけで購入してしまうリスクがなくなるわけです。
さらに同じ金額ずつ購入する場合、自然と株価が高いところでは購入数が少なくなり、株価が安いところでは購入数が増えます。
そのため、全体として株価を低く抑える効果も期待することができます。
より手軽にできる投資信託
今回は、株式投資にスポットを当てて説明してきましたが、より手軽に株式投資を行う方法として、投資信託についても触れておこうと思います。
投資信託とは、投資家のお金を一つにまとめてプロが運用を代行する金融商品です。
投資信託は商品ごとに運用方針が決まっており、株式に投資するタイプの商品であれば、日々の運用をプロに任せて、間接的に株式に対して投資ができるわけです。
投資信託には手軽ということに加えて、少額でも分散投資ができるというメリットもあります。
株式は一つの銘柄を購入するのにそれなりの資金が必要になるため、まとまった資金がないとなかなか分散投資はできません。
しかし、投資信託であれば、一口購入するだけでさまざまな銘柄に投資することも可能です。
なお、デメリットとしては、プロが運用を行うため、信託報酬という費用が差し引かれるという点が挙げられます。
メリットとデメリットの両面がある投資信託ですが、株式投資を行う際の選択肢の一つとして、頭に入れておくといいかもしれません。