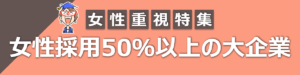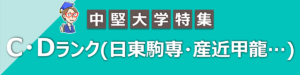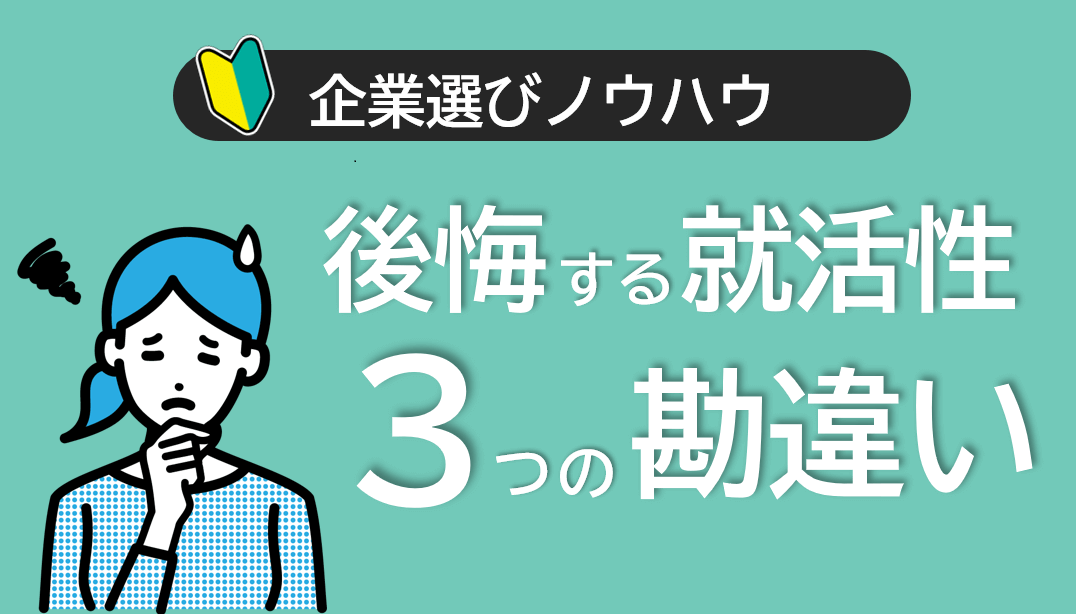就活は「最初の会社選び」で人生の土台が決まります。
1社目の就職先がその後のキャリアに与える影響はとても大きなもの。
しかしその1社目の就職に失敗したと感じている新卒入社の人は3人に一人と言われています。
多くの大学生が、見かけの「ラクそう」「安定してそう」という印象だけで会社を選んだ結果なのです。
この記事では、筆者が10年以上勤務した人材会社のノウハウでもある
「就活で失敗する就活生が陥る3つの勘違い」を紹介します。
あなたの未来を守るために、今、読むべき内容です。

1. 営業職を避ける就活生がキャリアで損をする理由
結論:営業を避けて就職した人は、20代のキャリア形成に失敗する。
昨今では、新卒の退職防止を目的とした人事・総務・経営企画などの管理部門への配属も増えていますが、企業を支えるのは営業職です。総合職として採用された場合は、どこかのタイミングで営業を経験することになります。
そのため面接の場でも「ストレス耐性」「やる気」「主体性」などがチェックされるわけです。
学生の中には営業職を「しんどい」「泥臭い」「頭を下げるのが嫌」と避ける人も多いのが現実。しかし、それは“最初から成長の機会を自ら放棄している”行為に他なりません。
営業職にも種類がある
営業=飛び込み、ガツガツという誤解がありますが、実際は以下のように多様です。
-
法人営業(BtoB)
-
個人営業(BtoC)
-
ルート営業(既存顧客中心)
-
インサイドセールス(内勤型)
-
コンサルティング営業(課題解決型)
向いていないと思っていた営業でも、スタイル次第で自分に合う形が見つかるかもしれません。

転職市場で評価されるスキルは「コミュニケーション力」がベース
文系職種で転職市場に出たときに最も評価されるのは、「対人折衝能力=コミュニケーション力」です。
私も経験しましたが、営業職を経験した人材は管理部門も欲しがります。
管理部門しか経験していない場合は高い専門スキルに加えて、チームとの円滑なコミュニケーション力を求められます。
営業職を避けた学生が配属されるのは、企画職・管理業務などに偏りやすく、結果的に転職やキャリアの幅で不利になります。

給与の上り幅は営業出身が有利
会社では、主任→係長→課長代理→課長…と役職が上がっていきます。
新卒入社なら横並びのスタートですが、係長クラス以降で営業職とそれ以外で差が出始めます。
最近はS職(スペシャリスト)やP職(プロフェッショナル)といった専門職コースも増えていますが、私が勤務する財閥系大手でもS職・P職に就けるのはごく一部。
結局、昇給するには役職を得るしかありません。その意味でも、成果が明確な営業職は有利です。
実際に経営陣を見ると、営業未経験者はほぼいないはずです。
また新卒入社で営業から始まっても、数年後に本社機能や間接部門へ異動することは十分にあります。営業は最初に経験すべき“土台”として最適なのです。

2. 「安定してそう」で子会社を選んだ末路
親会社依存の子会社は“安定に見えて”将来のキャリアを破壊する。
「親会社の名前がついているから安心」「安定してそう」と感じて子会社を志望する学生は後を絶ちません。
しかし、その選択は、将来的に転職やキャリアの自由を奪う致命的なミスに直結します。
理由①:親会社依存で主体性が育たない
親会社に予算も業務も依存している子会社では、重要な判断はすべて親会社任せになります。
企画、戦略、意思決定、採用に至るまで、親会社が指示し、親会社からの出向者が現場の管理職を担います。
その結果、社員は“与えられた仕事”をこなすだけとなり、ビジネスパーソンとしての主体性が身につきません。

理由②:転職市場で評価されない
子会社出身者は、転職市場でこう評価されます。
-
「意思決定経験がない」
-
「会社の方針に従っていただけ」
-
「グループ内の仕事しかしていない」
特に、外販比率(親会社以外からの売上)が7割未満の会社では、業務の9割が親会社対応です。
たとえば、グループ内の情報システム会社、保険会社、人材派遣会社、社内向けカスタマーサポートなどに多く見られます。
実績=グループ内処理だけでは、外の世界に出ようとしたときに通用しません。
理由③:親会社に依存する企業ほど将来“安定しない”
日本はこれから確実に人口が減り続ける市場です。
国内需要に頼り、親会社の発注ありきで成立している子会社は、その親会社の業績が悪化すれば即アウト。
現在は「安定しているように見えても」、10年後、20年後にはグループ全体が縮小し、リストラの対象になるリスクが非常に高いのです。

例外:独立採算で自立している子会社も存在する
もちろん、すべての子会社が悪いわけではありません。
たとえば、外販比率が高く、自立した事業部を持ち、独自ブランドや製品を展開している子会社は例外です。
ただし、そのような“真の独立採算型子会社”はごく一部。
大半は親会社の顔色を伺いながら動く組織であることを理解しておきましょう。
3. 新卒エージェントを頼った人が失敗する構造
エージェント任せの就活は「情報弱者のキャリア」に直結する。
「自己分析がうまくいかない…」「選考が進まない…」と不安になったとき、新卒エージェントを頼る学生は多いです。
一見、親身に話を聞いてくれて、企業も紹介してくれる。でも、その優しさの裏には、明確な“営業目的”があります。
理由①:紹介されるのは“採用に困っている企業”
エージェントのビジネスモデルは「学生を企業に紹介し、内定が出たら企業から成果報酬をもらう」という成果報酬型です。
つまり、エージェントが紹介するのは以下のような企業が中心です:
-
常に人手不足なアウトソーシング企業(SES)
-
親会社から独立できていない子会社
-
離職率の高い小規模企業
-
知名度の低いBtoBニッチ企業

理由②:学生の将来ではなく、自社の売上を優先
エージェントのKPI(評価指標)は「学生をどれだけ紹介し、内定を出させたか」です。
そのため、学生にとって最適な選択肢より「決まりやすい会社」を優先して紹介される構造になっています。
しかも、担当者も20代の若手社員が多く、社会人経験も浅いため、本質的なアドバイスは得にくいのが現実です。

理由③:「人任せ」の就活は、入社後にミスマッチを起こす
企業の情報を「聞かされた内容」だけで判断し、自分で調べず入社すれば、当然ギャップが大きくなります。
就職後に「こんなはずじゃなかった…」と感じる人の多くが、受け身のままエージェント任せにしていた人たちです。
正しいエージェントの使い方
エージェントを使うこと自体が悪いわけではありません。
重要なのは、“利用の仕方”です。
-
本命企業は自分で探す
-
エージェント経由では滑り止め企業の候補を絞る
-
大手の外販比率が高い企業を紹介してもらう
-
応募前に自分でも徹底的に調べる
ブラック企業回避のチェックリスト
紹介された企業が安心できるかどうかは、以下のポイントで必ず確認しましょう:
✔ 残業時間(月45時間以内)
✔ 離職率(3年以内で30%以下)
✔ 直近3年の業績推移(赤字続きは要注意)
✔ グループ企業ではなく、事業の自立性があるか

4. 【FAQ】就活で失敗しないためのQ&A
Q1. 営業が本当に向いていない場合はどうするべき?
A. 最初の1~2年は“修行”だと割り切ってやるべきです。向き不向きに関係なく、営業経験があることで他職種でも通用するスキルが身につきます。
Q2. 子会社でも大手グループなら大丈夫では?
A. 表面上のブランドでは判断できません。外販比率が低い会社や、親会社の下請け的な業務ばかりの子会社は避けましょう。
Q3. エージェントをどう使えば就活で失敗しない?
A. ES添削や面接練習など“補助ツール”として限定的に使いましょう。企業選びは自分で責任を持って行うべきです。
Q4. 本当に営業をやる必要ある?
A. 営業はキャリアのベースです。将来的に経営や事業責任を持ちたいなら、営業を避ける選択肢はあり得ません。
Q5. 親に「安定してる会社にしなさい」と言われました。子会社は安定してるのでは?
A. 親会社の業績に依存している時点で本質的には“自立していない企業”です。見かけの安定より「市場価値の高い経験」を優先しましょう。
5. 【逆質問】役員面接で使える逆質問テンプレート
逆質問は、あなたの「志望度」や「主体性」「思考力」を測るための面接官側の評価項目になっています。
質問をしない=関心が低い、受け身、準備不足と見なされる恐れがあります。
面接の逆質問は、ただの形式ではなく「最後のアピール時間」と考えましょう。
ここでは役員面接で使える逆質問の例をご紹介します。
-
「御社で活躍している若手社員に共通する特徴はありますか?」
-
「今後、10年後の業界変化に向けて、御社が求める人材像はどう変わっていきますか?」
-
「役員の皆様が新卒に期待している“成長の姿勢”について教えていただけますか?」
-
「グループ会社間のキャリアパスはどのように設計されていますか?」
-
「新卒が入社後3年間で身につけるべき能力は何だとお考えですか?」

6. 【模範回答】「最後に何かありますか?」への最強5選
面接官が「最後に何かありますか?」と尋ねる3つの理由
① 志望意欲の再確認
面接の締めくくりでこの質問をするのは、あなたの志望度が本物かどうかを確かめるためです。質問を通じて、どれほど真剣にこの企業を志望しているかを見極めようとしています。
② コミュニケーション力の最終評価
限られた時間内で、相手に配慮した質問や会話のキャッチボールができるかを見ています。ここでのやり取りは、あなたの対人能力の「最終チェックポイント」となります。
③ 個性や考え方の深掘り
これまでの質問で出せなかった“あなたらしさ”がにじみ出る瞬間でもあります。あえて自由度の高い質問をすることで、あなたの価値観や視点のユニークさを知ろうとしているのです。
「最後に何かありますか?」と尋ねられた時の最強回答5選
-
「ここまでの面接で私に対して懸念点があれば、ぜひご指摘いただけますでしょうか?」
-
「御社で早期に成果を出すには、どのような姿勢・行動が求められるでしょうか?」
-
「面接を通して、私のどの点が印象に残りましたか?改善すべき点もぜひ教えてください。」
-
「本日お時間をいただいたことに感謝します。もしご縁があれば、すぐに貢献できるよう準備を進めます。」
-
「若手時代のご経験で、今に活きていることがあれば教えていただけると励みになります。」
× 絶対に避けたいNG回答例
・「特にありません」 → 熱意ゼロに見える。準備不足と見なされる。
・「はい、ありません(沈黙)」 → 会話を終わらせる空気になる。非常に印象が悪い。
・「他の選考の結果によって決めます」 → 志望度が低いことを自分から宣言している状態。

7. まとめ:就活で後悔する前に、「3つの勘違い」を消し去れ!
就活失敗を招く3つの勘違い
× 1. 営業職はキツいから避けよう
→営業を避けた結果、ポジションも選択肢も狭まり、将来の転職市場で評価されない。
× 2. 子会社は安定してそうだから安心
→実態は親会社に依存しすぎて裁量がなく、キャリアの主導権が握れない。
× 3. 新卒エージェントに任せれば大丈夫
→エージェントは「企業の営業マン」であり、学生の将来ではなく契約成立がゴール。
どれも一見“正しい選択”に見えるからこそ、厄介です。
しかし、数年後に「騙された」と気づいたときには、取り返しがつかないこともあります。

就活は「どこに受かったか」ではなく、「どこでキャリアを築くか」が最終ゴールです。
自分の頭で考え、自分の人生に責任を持つ──それが、後悔しない就活への最短ルートです。