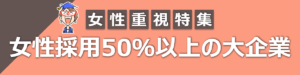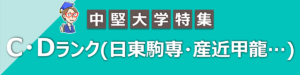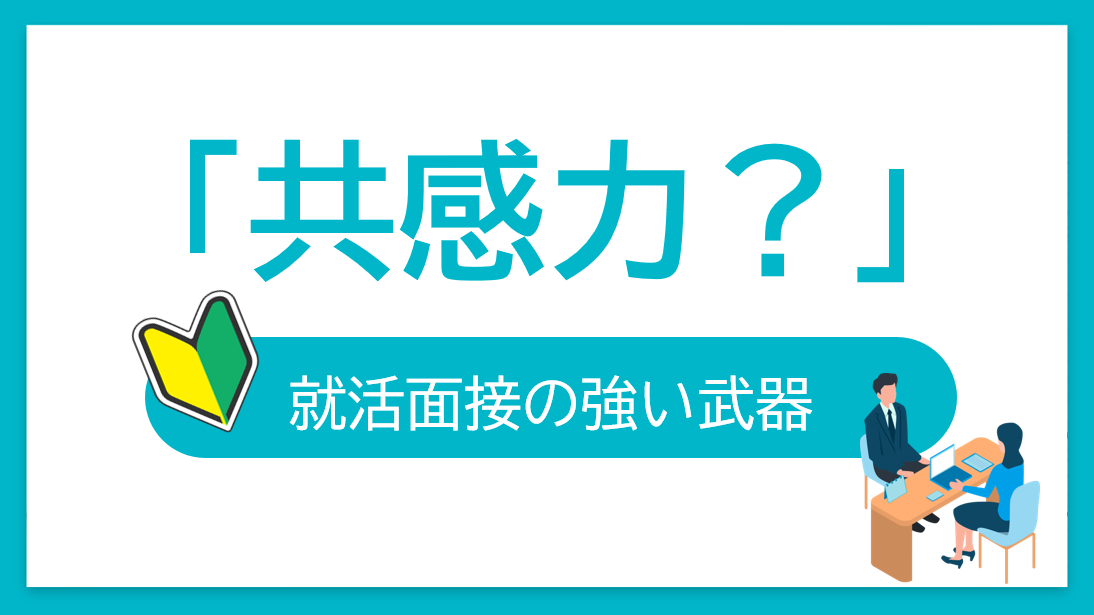今の時代、人を動かすためには「共感力」が必要になってきます。
正論を振りかざしたり、データで説き伏せようとしても、相手に反発されるだけです。
職場の人間関係を円滑にしたり、お客様からの信頼を獲得するためには、共感が欠かせません。
では、どうすれば共感力を伸ばすことができるのでしょうか。
心理学的の観点から、見ていきましょう。
なぜ今、仕事に「共感力」が必要なのか
コミュニケーション能力といえば、企業が求めるスキルの上位に常にランクインしているものです。
組織で働くともなると、周囲の人とうまく連携していくことが求められ、また取引先とも良好な関係を築くことが求められます。
そのような中で注目したいのが、「共感力」です。
これからの時代にリーダーシップを発揮したり、うまく人間関係を築いていくには、共感力が欠かせません。
「人間は論理的思考ではなく、感情で動いている」
とは、2017年に行動経済学によってノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授の言葉です。*1
理屈で説き伏せようとしても、相手は思うように動いてくれないことがほとんどです。
相手を動かすためには、その相手がどんなことに価値を感じているのかを知る必要があります。
相手を動かすカギとなる価値観や感情を感じ取るためにも、共感力は重要になってきます。
ただ価値観は、本当に多様です。
世代間の考え方や文化の違いなど、相手の考えを理解しようとしても、うまくいかないケースも出てくるでしょう。
だからといって相手を批判したり、価値観を押しつけるようなことをしてしまうと、相手からの反発を招いてしまうだけです。
多様な考えを持った人と仕事をしていくためにも、共感力は欠かせません。
ビジネスにおいては、自分の意見をハッキリさせないといけない場面が多いものです。
共感というと、自分の立場を曖昧にして、相手に同調するようなイメージがあるかもしれません。
しかし、共感といっても、八方美人になることではありません。
自分の意見や価値観はしっかり持ちながらも、自分と立場の異なる相手と関係を構築していく力が共感力です。
相手の感情をそのまま感じ取ることなどできるのか
他人に共感するというと、どうしても難しく考える人も多いでしょう。
その理由として挙げられるのが、
「他人が何を考えているのかわからない」
ということです。
他人が何をどう感じているのかを完璧に理解できなければ共感できないと考えている人も、多いかもしれません。
しかし実際には、共感するために相手が感じていることを完璧に理解する必要などありません。
そもそも他人の感情を完璧に理解することなどできるのでしょうか。
私たちは、他人が何を感じているのかを理解しようとする時に、無意識的に自分の過去の知識や経験を当てはめて理解しようとします。
つまり、自分の過去の知識や経験というフィルターを通して相手の心の中を解釈してしまうため、必ずズレが出てきます。
そのため、相手が感じていることを、そっくりそのまま自分も感じ取れるということは、まずあり得ません。
それでは、共感するとは、どういう状態なのでしょうか。
共感は、
「人と人とが関わり合い、互いに影響し合うプロセス」
のこととされています。*2
必ずしも相手と全く同じ感情を共有していなければならないというわけではありません。
相手が感じ考えていることと、自分が感じ考えていることが一致しなければ共感ではないということではないのです。
「共感」と似たものに「同情」があります。
アドラー心理学においては次に示すように、共感と同情は、はっきり区別されています。
| 共感 | 同情 | |
| 関係 | 相互関係・相互信頼 | 支配ー依存関係 |
| 関心 | 相手 | 自分 |
| 感情 | 信頼から始まりコントロールできる | 憐みから始まりコントロール不能になりがち |
引用)「アドラー心理学入門」岩井俊憲著 P103
共感は、相手と対等の立場に立つものであり、相手との信頼関係によって成り立つものです。
共感力について正しく理解することが、共感力を身につける第一歩です。
どうすれば共感力を身につけられるのか
それでは具体的に、共感力を身につけるには何に気をつければいいのかを見ていきましょう。
それにはまず、共感という点においてNGになってしまう例について解説します。
共感がうまく出来ないという人は、これらのNGになる行動を取ってしまいがちです。
それが、次に示す3つです。
①否定する
自分の方が正しいと思ったとしても、相手の言うことを否定してしまうと、その時点で相手との信頼関係を築くのが難しくなってしまいます。
相手には相手なりの考え方というものがありますので、それを尊重するという姿勢が重要です。
相手の考えを認めてしまうと、自分が間違っているかのように感じるかもしれませんが、それは正解は一つしかないという考え方があるからです。
人によって何が正解なのかは異なるということを受け入れることが大切です。
②説教する、意見する
先ほどの否定することと同様ですが、何が正解なのかは人によって異なります。
こちらの価値観や考え方を一方的に押しつけてしまうと、相手からの共感が得られないどころか反発されてしまいます。
相手との信頼関係を築くには、まずは相手の話をじっくり聴くという姿勢が大事になってきます。
③無関心
相手に対して関心が無いという状態では、共感は生まれません。
自分に関係のあることにしか興味が無いという状態では、自分本位になりすぎてしまう可能性があります。
相手に対して興味を持つというは、共感を生み出すための第一歩です。
共感は、オープンでフラットな関係によって成り立つものです。
共感力を身につけるためにも、この3つには注意しましょう。
このことが分かれば、共感力を磨くためのポイントも見えてきます。
「共感」は常に「受容」とセットになります。*2
無理に白黒をハッキリさせようとせずに、ありのままの相手を受け入れるというのが大事になってきます。
また、共感は対等な立場に立った信頼関係によって成り立つものです。
同情や説教のように、相手よりも上に立とうとしてしまっていないかには、注意が必要です。
さらに、相手が興味をもっていることに関心を示す態度のことを「共感的態度」といいます。*3
相手との信頼関係の構築には、共感的態度が欠かせません。
NGな行動に注意しつつ、ポイントをうまく押さえられれば、共感力を身につけることができるでしょう。
共感力を高めて人間関係を円滑に
共感は、人間関係を円滑にするうえで欠かせないものです。
先ほどご紹介した3つのNGな行動を周囲の人にやり続けてしまえばどういうことになるのかは、およそ想像がつくのではないでしょうか。
共感力は、SNS時代において、人と人のつながりを作っていくうえで大事な要素です。
最近では、SNSによって採用を行う企業もあります。
SNSを通して共感力の高さをアピールできれば、採用につながる可能性も十分あります。
それだけ企業も、他者への影響力を評価しているということではないでしょうか。
仕事は、人間関係が非常に重要です。
共感力が高まれば、人間関係が円滑になるだけでなく、仕事のチャンスも引き寄せられるようになります。
これからの時代に必要な力として、ぜひとも共感力を意識されてみてはいかがでしょうか。
【参考】
*1 )「マーケティングの本質」ADEX SYNRIラボ編著 P15