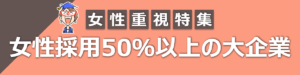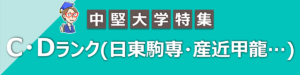クレカのリボ払いは、上手く使うことができれば便利な支払い方法です。
しかし、気を付けなければ使いすぎて支払いがなかなか終わらず、手数料(利息)を多く払うことにもなってしまいます。
リボ払いの仕組みやメリット・デメリットを正しく理解して、きちんと自己管理をしながら利用することが大切です。
そこで本記事では、リボ払いを利用する際、使いすぎにならないよう、上手な自己管理方法について説明していきます。
リボ払いの特徴は?分割払と何が違う?
リボ払いはクレジットカードの支払い方法のひとつで、毎月一定額を支払いしていく方法です。「リボルビング払い」を略し、「リボ払い」と言われることが多いようです。
クレジットカードの「分割払い」と混同する人もいるようですが、それぞれの違いを知っておきましょう。
「分割払い」はクレカ利用の都度、支払い回数を指定する方法(3回払い、10回払い、など)です。たとえば6万円の買い物をして、3回払いと指定すれば6万円に分割手数料を加えた額を3回で割って、3カ月にわたって支払いしていきます。
分割手数料は分割回数およびカード利用額に応じて決まります。
一方、リボ払いは利用額や利用回数にかかわらず、あらかじめ設定された金額を月々返済していく方法です。月々の支払額のなかにはリボ払い手数料(利息)が含まれています。
なお、リボ払いをするときの毎月の支払額の決まり方にはいくつかの方法がありますが、代表的なものとして「定額方式」と「残高スライド方式」の2つを紹介します*1。
・定額方式
クレカ利用金額および残高にかかわらず、毎月の支払額が一定となる方法です。
たとえば、毎月の支払額を2万円と設定していれば、残高がなくなるまで毎月2万円が口座から引き落とされます。
残高がなくならないうちに再度クレカのリボ払いを利用し、残高が増えた場合でも月々の支払額は変わりません。
・残高スライド方式
クレカ利用残高によって毎月の支払額が段階的に増減する方法です。
残高に応じた月々の支払額はカード会社によって異なりますが、たとえば次のように決められているとしましょう。
リボ払い支払額の例
| 利用残高 | 月々の支払額 |
| 10万円未満 | 1万円 |
| 10~20万円未満 | 2万円 |
| 20万円以上 | 10万円毎に1万円プラス |
この場合、15万円の買い物をしたときの月々の支払額は2万円。支払いが進んで残高が10万円未満になれば支払額は1万円に下がります。
もしも再度リボ払いを利用して、残高が10万円を越える(20万円未満)と支払額は2万円に上がります。
定額方式と残高スライド方式のどちらであるか、残高スライド方式の場合なら月々の支払額はどのように設定されているかは所有するクレカによって異なります。
事前にきちんと確認しておきましょう。
なお、買い物時に一括払いとリボ払いを選択できるのが一般的ですが、クレカによっては一括払いとしていたものを後からリボ払いに変更できるものもあります。
また、カード自体がリボ払い専用となっているものもありますのでしっかり確認しておくことが大切です。
リボ払いのメリットとデメリット
リボ払いの利用を検討する前に、リボ払いのメリットとデメリットを確認しておきましょう。
・メリット
毎月一定額を支払うリボ払いには、仮に大きな買い物をしてもまとめて支払う必要がなく、返済負荷を抑えられるというメリットがあります。
たとえば、予期せず急にパソコンの調子が悪くなったり、冷蔵庫が壊れたり、
「すぐに買う必要はあるけれど大きな額を1回で支払うのが難しい」
という場合などには便利です。
また一括払いで利用した後で、急に入り用ができるケースもあるかもしれません。
このような場合には、後からリボ払いに変更することで「支払遅延」を防ぐことができます。
支払遅延などのいわゆる「支払い事故」があると後々ローン申込みなどでマイナスの影響を受ける可能性がありますから、このようなリスクを避けることができます。
残高によって月々の支払額が変わる場合もありますが、一般的には支出額が一定ですから毎月の支出額を把握しやすく、家計管理をしやすいのもメリットでしょう。
・デメリット
月々の支払額のなかにはリボ払い手数料が含まれていることは前述しましたが、一般的にこの手数料は高めです。
リボ払い手数料の計算に用いる実質年率は所有するクレカによっても異なりますが、15%前後としているところが多いようです。
仮に実質年率が15%、利用残高が10万円とした場合、リボ払い手数料は次のように計算します。
前回支払い日から当月支払い日までの日数は30日とします。
10万円×15%×30日÷365日=1,232円(円未満切り捨て)*1
たとえば毎月の支払い額が1万円だとすると、元金の支払いに充てられる金額は8,768円のみ。毎月の支払い額が5,000円なら、元金の支払いに充てられる金額は3,768円になります。
クレカによっては月々の支払いをしやすくするよう、支払額を少額に設定しているものもあり、払いやすいものほど手数料負担が大きいことがおわかりいただけるでしょうか。
このように、元金部分と手数料部分の割合によっても支払期間が長期化しやすくなりますが、追加で利用すればさらに支払期間が延びてしまいます。
リボ払いの使いすぎを確認するには?
「一定額」「払いやすい」という特徴から、リボ払いは使いすぎのリスクもあります。
使いすぎると支払いが長期化するほか、必要な時にカードを利用できなくなる可能性も考えられます。
クレジットカードにはカードごとに利用可能枠(与信枠)が設定されていますが、リボ払いで残っている利用残高は与信枠を使っていることになります。
毎月支払いしていても元金の減りが遅ければ、あらたに利用できる額も小さいままとなってしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、リボ払いを利用した場合には、利用明細やクレジットカードのサイト(マイページ)で定期的に次のポイントを確認しましょう。
・利用残高
・毎月の支払い額に対する手数料額
・毎月の支払い額に対する元本と手数料の割合
・完済時期(追加利用がない場合)
とはいえ、これらがいくらであれば「使いすぎ」なのかは一概には言えません。
場合によっては手数料を払っても一時的にリボ払いの利用を要される人もいますし、人それぞれの状況で異なります。
それでも「無駄な手数料を払っているかもしれないのでは?」と自問するクセはつけたいものです。
先に見た例では1万円のうち手数料は1,232円となっていましたが、12%以上の手数料を払っている計算になります。
大手都市銀行の定期預金金利相場が0.002%*2ですから、約6,000倍の金利です。
家計収支の状況やリボ払い利用の必要性、今後のライフプランで必要となる資金の準備要否などに照らし合わせて、リボ払いを使うことの是非、使いすぎかどうかなど、自分なりの正解を出せるのではないでしょうか。
・効率的に返済する方法を知っておこう
リボ払いの月々の支払い額は利用しているクレカによって決められていますが、繰り上げ返済や増額変更により、決められた支払い額より多く支払うことは可能です。
多く払えば利用残高がその分減ることになりますから、次からの手数料も低減させることができます。
使いすぎが気になっていたり、完済を早めたい場合には、家計に負担をかけすぎない方法で少しずつ支払いを早めていきましょう。
・繰り上げ返済
残高の全部または一部を繰り上げて返済できます。
月々の口座引落日にかかわらず、振込やATMなどで随時返済可能です。
ただし、振込する場合には、削減できる手数料額と、振込手数料の大小も必ず比較して行うことが大切です。
・増額変更
月々の支払い時にいつもよりも増額して支払う方法です。
たとえば毎月の支払額が1万円のところ、次月は3万円引き落としてもらうように変更手続きする方法です。
「随時」の増額申込みであれば、その翌月は1万円に戻ります。
大きな額は支払えなくても毎月の返済額を1000円、2000円でも増額していけば予定よりも完済は早まります。
たとえば、毎日缶コーヒーを買っている人は回数を減らす、タバコを吸っている人は本数を減らすなど、さまざまな工夫で月数千円を浮かすことはできるはずです。
このような方法ならお小遣いのなかで支出を減らせますし、仮に家族に知られたくないという人などにも実行できそうですね。
・きちんと自己管理をしながら、必要に応じて上手に利用しよう
リボ払いは利用に関して注意すべき点が多々ありますが、利便性もあり、家計収支の状況によって利用を検討してみるのもいいでしょう。
ただし、リボ払いの特徴を知るとともに、自分で利用ルールを決めて上手に利用することが大切です。
メリットとデメリットの両方を兼ね備えているのがリボ払いです。自己管理を徹底し、利用するなら上手な利用を目指してください。
*1:一般社団法人日本クレジット協会「リボ払いの特徴と利用上の注意」
*2:三井住友銀行「円定期預金金利」